 日本が抱える課題については、論者によって様々な見方がある。私の問題意識の根底にあるのは、日本人のものの考え方、物事への取り組み方がいまだ〝昔〟に基準を置いていることから全然抜け出していない状況でよいのだろうかという危機感だ。
日本が抱える課題については、論者によって様々な見方がある。私の問題意識の根底にあるのは、日本人のものの考え方、物事への取り組み方がいまだ〝昔〟に基準を置いていることから全然抜け出していない状況でよいのだろうかという危機感だ。日本は、現状に対する認識が非常に曖昧で、現実を徹底して突き詰めようという執念に乏しい。しばしば願望や希望を織り交ぜながら、何となくぼんやりしたものに寄りかかって問題を考えたり議論をしたりしている。その結果、無意識に使われている『失われた○○年』という言い回しにも、暗に『元に戻る』というニュアンスが含まれている。『あの頃は良かった』モードで昔の未来を繰り返し、逆回転しているような感じからなかなか脱することができない。
根拠がなく、なんとなく「日本は例外だ」と逃げ込んでいてはだめだ。現実は常に動いており、日本は他国よりはるかに速いスピードで、急速な人口減少や高齢化という大きな変動を体験している。しかも今、我々が臨んでいるのは前例のない事態で、他所からモデルを持ってきて「ここではこうなっています」では済まない問題も多い。暗い話に皆うんざりだというのはわからなくもないが、やはり人間の認識というのは現実にぶつかる都度、鍛えなければいけない。これからの時代を担う若者も勉強する必要があるが、上の世代の人たちも、若い人たちが直面している現実にもう少し寄り添ってものを考えていかなければ、話が空回りするだけだろう。日本アカデメイアの一つの役割はこういうところにある。
大局観が欠落し、根っこの方から鍛えなければいけないという兆候は、政治の世界にも顕著に表れている。目先のことや、ああすれば良くなる、こうすれば良くなるという、やたらと景気の良い話が繰り返され、あるいは、国民に夢を語るのが政策だ、という感覚が抜けない。
 人口構成も雇用環境も所得も分配も昔とはかなり状況が異なる。今後の見通しについても、人口減少はもちろん、財政問題や貯蓄率の低下等、歴史の歯車は我々の前途にかなり厳しい予見性を与えている。残されている余裕、選択の余地がいかに狭いかを踏まえ、ギリギリのシナリオで、どのような展望が持てるかを考えなければいけない。
人口構成も雇用環境も所得も分配も昔とはかなり状況が異なる。今後の見通しについても、人口減少はもちろん、財政問題や貯蓄率の低下等、歴史の歯車は我々の前途にかなり厳しい予見性を与えている。残されている余裕、選択の余地がいかに狭いかを踏まえ、ギリギリのシナリオで、どのような展望が持てるかを考えなければいけない。厳しい現実を共通認識として持った上で、しかしなお、敢えて少し動かしてみよう、こういう可能性は追求してみよう、これがボトムでやりようによってはそんなこともできるかもしれないと競争することがこれからの政治に求められるはずだ。見たくないものを直視する精神的強さがないと、結局ズルズルと目算もなく、無駄で非効率な手を打つことになる。
また、今日的課題を解決するためには、政治と経済がより密接に連携を深めることが欠かせない。しかし、政権の現実認識というものが、たとえば経済界とどの程度共通性があるのか。お互い徹底的に議論を詰める、あるいは議論を詰めた上で協力しようという段階にまで、この国はまだ至っていない。やはり政治家が、もう少しそういう現実認識に対してエネルギーを使うべきだろう。

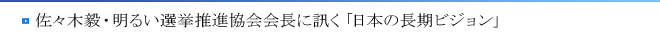
 政治にまつわる問題は、国会・内閣の改革から選挙のあり方まで多岐にわたり、お互い複雑に絡み合っている。時間軸を念頭に置き、短期、中期、長期に分類・整理し、取り組むことが肝要であるが、日本の政治が長期的課題に対応できる体制に生まれ変わる上で最終的な課題となるのは政党のあり方だ。
政治にまつわる問題は、国会・内閣の改革から選挙のあり方まで多岐にわたり、お互い複雑に絡み合っている。時間軸を念頭に置き、短期、中期、長期に分類・整理し、取り組むことが肝要であるが、日本の政治が長期的課題に対応できる体制に生まれ変わる上で最終的な課題となるのは政党のあり方だ。